近所で悪臭や害虫が発生する「ゴミ屋敷」に悩んでいませんか?
「ゴミ屋敷を法律で取り締まって!」そんな風に考える方も多いでしょう。
本記事では、ゴミ屋敷に適用できる法律の考え方や、全国各地の自治体が独自に制定している「ゴミ屋敷対策条例」を紹介しながら、現実的な解決策を解説します。
ゴミ屋敷は放置しておくと、火災のリスクもあるので大変危険です。
この記事を参考にして、今すぐゴミ屋敷問題を解決していきましょう。

不用品回収隊
不用品回収隊は「愛知・岐阜・三重」を対象エリアとする不用品回収業者です。業界最安級の価格に加え「頭金0円・現金分割払い(最大60回分割)対応可」と支払い方法も柔軟に対応しております。WEBからのお申込みで20%オフで利用できるキャンペーンを実施中ですので、お気軽にお問い合わせくださいね。
この記事を書いた人
ゴミ屋敷問題に関する法律はない!
結論から言えば、日本には「ゴミ屋敷そのもの」を直接取り締まる国の法律は存在しません。
たとえ自宅内や敷地内に大量のゴミがあっても、本人がそれを望んで生活している限り、法的に罰することは基本的にできないのです。
憲法で保障されている「居住の自由」や「私有財産の保護」といった基本的人権が優先されるためです。
行政や他人が無断で介入したり、強制的に片づけたりすることは原則として許されません。
そのため、ゴミ屋敷に直接的に法的措置をとることは不可能なのです。
ゴミ屋敷の法的定義ってあるの?
「ゴミ屋敷」という言葉は日常的に使われていますが、実は法律上における明確な定義は存在しません。
つまり、どれくらいゴミがたまったら「ゴミ屋敷」とされるのか、法律的なラインは引かれていません。
そのため、行政や警察が介入できる基準も、法律上ではなく、あくまで地域の条例やケースごとの判断に委ねられています。
ゴミ屋敷問題は法律ではなく条例によって対処できる
ゴミ屋敷問題に対して、国の法律ではなく、各自治体が定める条例(条令)によって実際の対応が行われているのが実態です。
ゴミ屋敷が周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすようなケースでは、行政が動けるように独自のルールを条例として設けている自治体が増えています。
一方で、ゴミ屋敷に関する条例が整備されていない地域では、行政による強制対応ができません。
そのため、近隣住民が長期間にわたり被害を受け続けるケースが多いのです。
次章で、実際のゴミ屋敷問題に関する自治体の条理を紹介します。
ゴミ屋敷問題の全国自治体の条例を一部紹介
全国的にゴミ屋敷問題が深刻化する中、実効性のある対策として独自の条例を制定する自治体が年々増えています。
ここでは、実際にゴミ屋敷対策条例を定めている自治体の一部を紹介します。
地域ごとの方針や対応の違いにも注目することで、自身の地域の対応状況を確認する手がかりにもなるでしょう。
①東京都足立区
東京都足立区は、2013年1月にごみ屋敷問題に特化した『足立区生活環境の保全に関する条例』を交付しました。
住民の生活環境を著しく害する状態としてゴミ屋敷を位置づけ、助言・勧告・命令・代執行までのプロセスを明文化。
再発防止にも力を入れており、他自治体のモデルにもなっています。
②大阪市
大阪市は『大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例』で、ゴミ屋敷およびゴミの放置を取り締まっています。
そのため、必要に応じた代執行が可能です。
住民が通報すればすぐに行政介入となるので、隣人のゴミ問題がでてて来ても安心です。
③京都市
京都市の『京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例』は、市民の快適な生活環境を守っています。
また、ゴミ屋敷に住んでいる人のケアやサポートも丁寧に支援することをモットーとしています。
本人への寄り添いを大切にし、ゴミ屋敷問題の根本から解決しているのが特徴です。
④福島県郡山市
郡山市には『郡山市建築物等における物品の堆積による不良な状態の適正化に関する条例』が定められています。
ゴミ屋敷を放置せずに適正化することにより、市民の安全で安心な生活環境を確保しています。
市長の指示があればすぐに行政の介入が可能です。
市民はゴミ屋敷問題に困ったらすぐに市に連絡を入れると良いですね。
⑤愛知県豊田市
愛知県豊田市では『豊田市不良な生活環境を解消するための条例』を制定しています。
空き地のゴミ屋敷問題にも積極的に解決を行っています。
行政による是正勧告が行き届いているので、住民も安心して過ごせるでしょう。
なお、他のゴミ屋敷対策事例を見たい方は、以下のサイトもご覧くださいね。
今回紹介した自治体以外にも多くの事例があるので、参考になるはずです。
条例がない場合のゴミ屋敷の対処法は?
「うちの自治体にはゴミ屋敷対策の条例がない…」と悩む方も少なくありません。
条例が整備されていない地域では、行政が強制的に介入する法的根拠が乏しいため、対応が難航するのが現実です。
それでも、周囲に被害が出ているようなケースでは、いくつかの法的・現実的な対応策があります。
民法を使って「不法行為」として損害賠償請求
ゴミ屋敷が原因で、悪臭・害虫・火災リスク・精神的苦痛などの被害を受けている場合、民法第709条の「不法行為」に基づいて損害賠償請求や撤去の訴訟を起こすことが可能です。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
出典:民法|第七百九条
特に、隣接住民である場合は、被害の証拠(写真・臭気・診断書など)を集めることができます。
個人での対応が難しい時は、弁護士への相談も検討してみてもいいでしょう。
保健所・消防・警察への通報
健康被害や火災リスクが想定される場合は、保健所や消防署、警察へ通報することで行政調査が入る可能性が高いです。
たとえば以下のような状況があると、対応が進む可能性が高まります。
- 害虫や悪臭がひどくて生活に支障がある
- ゴミが道路にはみ出している
- 放火や火災の危険がある
- ゴミを周囲に投棄している
(=廃棄物処理法違反の疑い)
ゴミ屋敷が引き起こす危険な火災・害虫トラブルを予防する方法をまとめた記事もあるので、ぜひ参考にしてみてください。
記事を読んで「やはり危険だ」と思ったら、すぐに通報しましょう。
地域包括支援センターや民生委員へ相談
高齢者や独居者がゴミ屋敷化している場合は、福祉的なアプローチも有効です。
地域包括支援センターや民生委員が家庭訪問や生活支援を行い、間接的に改善へつなげることもあります。
本人が片付けを拒否していても、信頼関係を築くことで協力的になるケースも少なくありません。
ゴミ屋敷問題の法律はないため自治体の条例に頼ろう

ゴミ屋敷問題は全国的に深刻化していますが、現時点で日本の法律には「ゴミ屋敷そのもの」を直接取り締まる条文は存在しません。
つまり、国の法律だけでは強制的なゴミ屋敷の片づけや罰則といった法的措置は行えないというのが現実。
このような中で、実効的な対策として注目されているのが、自治体による「ゴミ屋敷対策条例」です。
条例が整備されている地域では、助言や指導、勧告、さらには強制代執行まで段階的な対応が可能になっており、近隣住民の安心につながっています。
一方で、条例が整備されていない地域では、迅速な対応が難しいのが実情です。
ゴミ屋敷問題に直面した場合は、まずは自治体の条例の有無を確認しましょう。
必要に応じて保健所・消防・民生委員・弁護士などの専門機関へ相談することが重要です。
また、ご家族や身の回りの方でゴミ屋敷問題に悩んでいる方がいたら、一度民間サービスに頼ってみるのも良いでしょう。
不用品回収隊は無料見積りも受け付けているので、気軽に相談するだけでも問題ありません。

不用品回収隊
不用品回収隊は「愛知・岐阜・三重」を対象エリアとする不用品回収業者です。業界最安級の価格に加え「頭金0円・現金分割払い(最大60回分割)対応可」と支払い方法も柔軟に対応しております。WEBからのお申込みで20%オフで利用できるキャンペーンを実施中ですので、お気軽にお問い合わせくださいね。
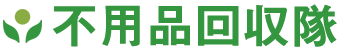




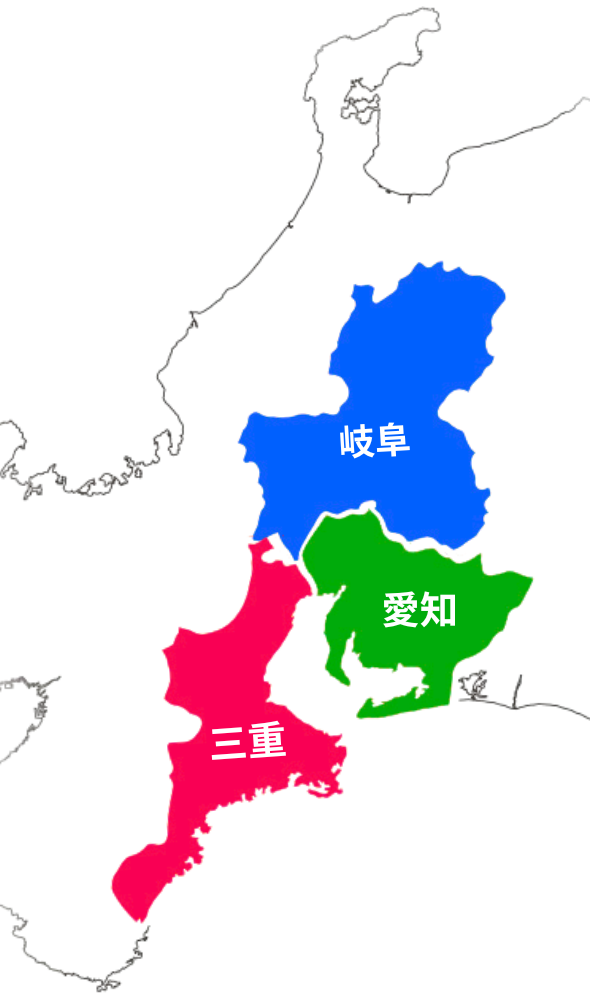


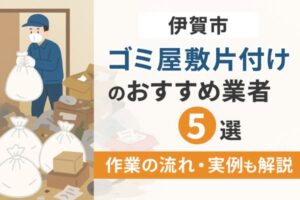







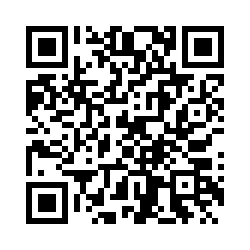

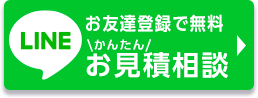
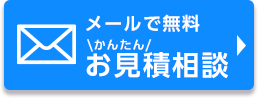
コメント